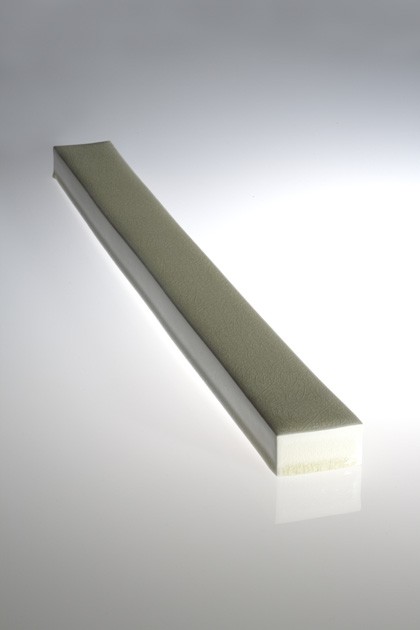茶事は何回やってもなかなか満足が得られない。うまく行ったためしがないと言ってもよい。もてなそうという心はあるのだが、虚栄心が先立ってしまう。機知やユーモアを発揮しようとしても、下手な芸人のようにずっこけたりする。気のきいたことも吐けずしどろもどろとなる。要はええカッコがしたいのである。終れば疲労と自己嫌悪が待っている。しかし、たまさか調子が良かったりすると点前をしながら快感を覚えることもある。リズムを感じるのである。ジトッとしたリズムなのだが、それが緩急をつけながら、破綻なく続いていく感じである。五体の末端までが脳ミソの指令に従って、微妙なミリ単位の動きに応じていく。ある種の勁(ツヨ)さをもって静かに舞っているような心地ぞするのである。濃茶の練り具合などもうまくいくと、一種のどうだ!という気持ちになったりする。しかしこれも独りよがりの自己満足に過ぎないような気がしている。レベルが低いのである。
利休織部宗二は三人とも死んでいる。ほとんど同時に茶の湯に殉じるようなかたちで、申し合わせたように死んでいる。はかりごとを帷幄(イアク)にめぐらすというが、そんな感がある。多分にポリティカルな死でもあったのだろうが、士はおのれを知る者のために死ぬということがある。次第によっては命よりも大事なものがあるという人間行動の一証左であろう。その三人が寄り合い、死を予感し、死を覚悟し合う場面を描いた小説がある(井上靖の本覚坊遺文、映画化もされた)。夜咄の茶事だったか、小説、映画ともその場面の尋常ならざる緊張感はいまだに印象に残っている。その茶事が実際にあったものかどうかは知らないが、あったとすれば、禅の公案のごとく提出された課題は、難問中の難問、死である。延々続くかと見えたところで、だれかが大喝を入れてやっと静まるようなものだったのではないか。そのとき一座は建立してそびえ立っていたことだろう。茶事は弛緩ではなく緊張であらねばならぬということの頂点を示している。それにしてもこんな世離れした茶事にはどのような道具が使われることになるのだろう。映画では無という掛物がかかっていた。茶碗は長次郎の黒だろうか。
茶とは風流韻事であり、それとして楽しみ、教養のようなものを養うということで一向結構なのだろう。また修練という意味では自衛隊の体験入隊のような効用もあるのかも知れない。しかし凡夫凡婦があのような、洗練はされていても、型にはまった手順を何度くり返してみても、つまるところ何が得られるのだろうかと、おのれをかえりみて思うことがある。茶事を持つには目的が要る。その目的が現代ともなればなまぬるいのかも知れない。見つからないのかもしれない。彼の人たちがなしたような、ツーアウト満塁のような追い込まれた状況でのプレーなど出来るはずもないのだろう。要するに私たちはなぞってくり返しているに過ぎないのである。手順をぶち壊して一度バラバラにするような力も私たちにはないだろう。完成されたものに些事を付け加えてきただけである。しかしこれでは面白くないのである。茶事をやっていても緊張感がないのである。水屋でタバコなど吸ったりしている(筆者です)。
こうなればハプニングを仕組まねばなるまい。仕組まずともハプニングはたまに起こることは起こる。水指の共蓋が少し小さくてトポンと中に落としたことがある。あの音はよかった。足がしびれ過ぎて爪先立った客が湯斗の鬼桶に足を突っ込んだりもある。これも一つの波瀾である。そこで茶事の流れがいったんぶち切れるということで、一種のパニック状態が現出される。しかしその混乱を収拾しようとするところに亭主の人間の片鱗が垣間見られるかもしれないし、客だって一緒に笑ったりハラハラしたりもするだろう。まあとても低いレベルではあるが、そこには一瞬にせよ一座建立に似た空気が流れるのではないか。絶交されるだろうが、筆者は一度落とし穴を掘ってみたいと思う。または丿貫(ヘチカン)のひそみにならって女装してみたいとも思っている。
葎
JUN AKIYAMA
1970年生まれ
1999~2002 鯉江良二に師事
2002 韓国慶尚南道で作陶をはじめる
現在は慶尚北道にて制作
所蔵:韓国利瑛美術館